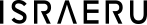「日本語でPHOTOGRAPHって、写真っていうんでしょ?美しい言葉だね」
ある日の撮影現場に向かう道中、そう言ったのはイスラエル人写真家のShimon Bokshtein(以下、シモン)。

彼はシャイで、言葉数が少ない。
そんな彼が写真という日本語を知り、感動を口にする姿に、私自身気にもしていなかった奥深さに気付かされた。
写真家とは、被写体の内に秘められた真なるものを写し出す、そんな職業なのだと身を持って教わった瞬間だった。

そんなシモンと、彼から学んだ私なりの「写真」の真意の考察を、彼の美しい作品と共に綴りたい。
目次
「写真家」として生きる
【Photographer: Shimon Bokshtein】
ネゲヴ砂漠、ミツペラモン在住。
写真はもちろん、映像監督もこなす。ポートレートや風景写真、ドキュメンタリーフィルムはもちろん、手法に拘る事なく独特の世界観で自由に形を変えながら作品を発表している。
彼の作品からは、純粋で素直、控え目で自然体、リアルで抽象的、壮大でいて繊細、そんな印象を受ける。

写真家の活動以外の側面もたくさんあって、今でこそアパートの一室を借りているが、電気も水道もない砂漠の中で愛犬と暮らし、灌漑農業のワイン畑で働いたり、遊牧民のバドウィンと共に暮らしたり等、プリミティブに生きながら、砂漠地域のアート活性化で町おこしをする活動等も行なってきた。
週末にはデモの撮影や、アラビア語の練習に勤しむなど、平和活動にも意欲的だ。

筆者の私は、そんな彼がまだ砂漠に越してきたばかりの頃に出会い、次第に周りから写真家と呼ばれていく過程を、アート活動を共にすることで見つめてきた。
「僕、写真を撮りたいんだ」といいつつも、電気がなくてパソコン作業もできない砂漠にいる。そんな彼は、時々滑稽だった。

シモン「君が知ってるように僕の作品づくりは、今も昔と変わっていない。あまり何もしていないよ。笑」
その技法とは、演出をほぼ決めずに被写体と撮影地に向かい、目に見えるもの全てを視野に入れて撮り始める。即興的に生まれてくるものに、その場で反応して、形や物語が決まっていく。

強いていうなら、自然の流れを壊さない努力をしているように見受けられる。シモンは撮影現場でも、私生活でも、少し控え目だ。

私「じゃあ、その中でシモンが一番大切にしているものは、何?」
シモン「繋がり。
シャッターを切ることは、誰でも出来る。
特に今の時代、簡単に写真を撮れる。
パーソナルな繋がりがあるかどうかが、大事。
ANDARTAのように・・・。」
彼がいうANDARTAとは、筆者がダンサーとしてシモンと共同制作したダンス映像作品「ANDARTA」だ。

イスラエル人の彫刻家DANI KARAVAN作のネゲヴ砂漠戦没者記念碑「ANDARTA」を舞台にしたこの作品は、2019年にルーブル美術館から受賞し、その後世界各地で上映されてきた。 撮影当初は、構成も演出も(強いては、作品にするかどうかすら)何も決まっていなかった。しかし、偉大な砂漠と、そこに聳え立つ彫刻に降り立った瞬間、シモンは自然と撮り始め、私も踊らされていた。次第にクリエイター達が集まり、目に見えない「繋がり」が、紡ぎ出されるように、一つの作品が出来上がった。
まるで、自然現象。神助けの様な追い風すら感じた。私は、その力の源こそが、写真の持つ本質的な要素なのだと、後々わかってきた。

おすすめ記事
ヘブライ語の「צלם (写し)」
各信仰の共通点
「写真」は、ヘブライ語でצילום(Tilum)という。
その語源は古く、ユダヤ旧約聖書の創世記に由来し、神は自身のצלם(Tzelem)から人をつくったという内容の記述がある。
英語ではよく「イメージ」と訳されてしまったこの言葉の真意は、案外見逃されていると思う。
「צלם 写す」
とは、コピーペストではなく、模倣でもない。
日本神道でいうところの神の本体として鎮座している「鏡」と同じものであると、私は思っている。
鏡に写るのは、自分自身の姿を通した本質の現し、つまり真我だ。そして、それは神様(真実)に通じている。神道では「直霊(なおひ)」といい、私達自身に神様の欠片が入っているのだ。
内なる自分の本質に神を見る、絶対的な己への信頼と自然との共感がそこにある。
仏教では、心は鏡と同じ役割をしているといい、好き嫌い等の執着も無くし、ただ「写す」ことが重要とされる。
いついかなる時でも、この状態に立ち返る事が出来れば、それは瞑想の完成といわれる。
自然への畏敬の念から、この世の全てに神がいるとするアメニズム信仰も「ありのままと繋がろう…一体となろう…」といった、真実を自らに映そう(=移そう)という試みそのものだ。大和言葉においては、読み方が同じ漢字の真意は共通する事が多い。
つまりこれらは全て、人類の初の初なる段階でつくられた…。
それが「צלם =写し=Photograph」なのだ。
シモンの写真が美しいのは、シャッターを切るその瞬間、彼が真なる我(自己)へ繋がり、それを写し出しているからなのかもしれない。

ロシア移民としてイスラエルで生きる選択
シモンは、1985年生まれ。サンクトペテルブルグ出身。ソ連崩壊を幼い頃に経験し、15歳の頃、一人イスラエルへ帰還した。

母国語はロシア語。ヘブライ語は、ユダヤ人学校や、家族の間で少しだけ話していたが、大部分はイスラエルに来てから勉強した。
私がイスラエルで出会った頃のシモンは、英語がままならず、互いに片言のヘブライ語だけで意思疎通した。
ソ連崩壊直後のサンクトペテルブルグでは、既に英語教育は組み込まれていたらしいが、話せる周りは少なかったそうだ。
イスラエル統計局によると、同国にいる旧ソ連圏移民の内、約25%は、ヘブライ語を話せず、その内、家庭での会話をロシア語のみで行う移民は、約50%に至るという。
シモン「やっとヘブライ語を話せるようになったと思ったら、英語が話せないし、ロシアではユダヤと呼ばれ、イスラエルではロシアと呼ばれる。」
多くの移民系イスラエル人が抱えている事情だが、ロシア系のそれは、イスラエル社会において根が深い。 シモンがいうには、ペレストロイカまでの旧ソ連は、シオニズムがご法度で、そこにいるユダヤ人達は、まるで骨抜きにされた様で、雇用面でも大きく社会からハンデを持ち、アイディンティが脅されたそうだ。シモンの家族も、貧しかった。
そんな中、旧ソ崩壊が引き起こした経済パニックで、人によっては半ば死に物狂いで脱出してきたにも関わらず、彼らの存在はイスラエルでは、シオニスト精神に欠けるロシア移民といった目で見られ、ユダヤ人同士の中でも精神的壁なるものがある一面は、否めない。

シモンの家族は、そんな移民に躊躇していた。
先に、新天地イスラエルで一人生活し始めたシモン。高校生活を終えて、入隊式が待っていた、そんな折、サンクトペテルブルクに残してきた祖父が亡くなった。
シモン「おじいちゃんの写真(記憶)がなかったんだ。
悲しかった。
だから写真を撮ろうと思った」。

幾つもの苦しみが重なったことは、想像に難くない。
この話題をそれ以上しないシモンは、続けてこう呟いた。
「ダンスは現在の連続だけど、写真は未来と過去しか生きられない・・・」。
撮影する時は、未来の編集の都合を考え、出来上がった作品は、その瞬間に過去の産物となると、そんな思いらしい。
私はこう思う。
大国の崩壊と貧しさを経験し、帰還を成し遂げるが、居場所のなさや家族との別離を嘆く余地もなかった、そんなシモンが自らの命に繋がって導き出した「写真を撮る」という答えは、その瞬間(現在)に写されたシモンの真の心の現れで、それが未来を創造し、過去の意味をも変えている…。
イスラエルの未来はもちろん、彼の愛した祖父の人生、強いてはソ連という大国の元に翻弄された多くの命の意味付けも、変える力があるのだ。
写真とは、現在から写し出され、どんな時空をも生きている真理ではないだろうか。
体感芸術が得意芸のイスラエル
ユダヤ神聖幾何学はホログラム
更に私は、神のצלםTzlemとは、「真」というホログラム(物質化する前の型)へ辿り着く方法と考えている。
そのホログラム型を意識し写し出すと、リアルな形を陽炎の中から出現させる。

まるで、写真のネガとポジを結ぶ映写機のような役割が「צלם Tzlem」。ユダヤでは神聖幾何学が発展したが、その理由も根源的な型の追求だったのではないかと考えられる。
シモン「砂漠が好き。
なにも無いようで、いつも全てがある」
自然界には究極にシンプルな型があり、それは写し方次第で、無限に意味を生み出し、感じとる事が出来ると示唆している風に考えられないだろうか。
この写しの意識は、様々な文化や文明で形を変えながら、人々を導いてきたようだ。
武道の身体意識では、鏡の役目は「下丹田」であると教わった。
丹田の「丹」は、ヘブライ語の神(ヤハウェ)のスペルに等しく、その文字の形は鳥居の形そのものだ。そして、この「丹田צלם」を身体的にリアルに意識するには、やってみればわかるのだが、煩悩などは存在し得ない。
これが、ユダヤの教えには懺悔はあっても、煩悩や忍耐の内容や対処についての言及がない理由だと考えている。
身体の意識をユダヤ風に磨いていくことは、苦しみや葛藤の直接的な解決にはならずとも、その瞬間毎に、全く違う神域に至ることを体験できる。
これがイスラエルで体感的芸術が発展した理由だと捉えている。
神職としての写真家
シモンは、結婚式等の催事関連の撮影の仕事も自ら進んで行っている。
(詳しくは、彼のウェブサイトから問い合わせができるので、参照されたい)。
Shimon Bokshtein Website
これらの現実的な繋がりある活動が、具体的に人々の心に影響する。 祖父の遠い記憶を初動に、シモンは人々を写し出す。
“If I could tell the story in words,
I wouldn’t need to lug around a camera”
(言葉で語ることができるなら、カメラを持ち歩く必要はないだろう。)
Lewis Hine
今、この瞬間も一枚の美しい写真のような現実が浮かび上がっているのだと気づかせてくれた。
天然たる藝術の現れ、それがシモンの「写真」ではないかと私は思っている。

「ANDARTA」