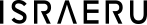日本人にとって折り紙はとても身近なもの。「保育園や学校で折り紙を手にしたことがない」という日本人は少数派でしょうし、「国際親善交流会で折鶴を折って披露した」という経験を持つ方も多いのではと想像します。
そんな、日本の代表的な伝統文化の一つである折り紙。けれど今の日本で、どれほどの人が折り紙が持つ本当の力を活用しているでしょうか?実はイスラエルは世界で唯一、折り紙を使った幾何学の学習プログラムが教育庁に認可されている国なのです。
折り紙を使った幾何学教育の立役者、「イスラエル折り紙センター」を運営する折り紙芸術家のミリ・ゴランさんに、お話を伺いました。

―――まず、折り紙との出会いについて教えてください。
ミリ:私と折り紙の出会いは本当に偶然でした。私が子供だった頃、まだ白黒のみだったテレビの放送で教育プログラムの時間があり、そこで折り紙で作る「鶴の折り方」が放映されていました。
単に「外国の文化の一部を紹介する」程度の番組だったと思います。何の気なしに、手元にあった紙をとって、一緒に折りました。
そこからです。私はいつでもどこでも何かしら紙を折るようになりました。折っていると集中力が増したのがわかりました。
1989年に日本を訪れた際は、折り紙センターを探しました。観光庁のビジターセンターで折り紙センターを案内してほしいと言ったら、「そんなものはない」と言われてしまいましたが。(笑)
そこで私は本屋に行って、ありったけの折り紙の本を買ってイスラエルに帰ったのです。
―――その後、イスラエルで折り紙センターを開設したのですね。
ミリ:はい。日本旅行からイスラエルに戻って自分の進路を考えた時、私は教育について学んだし、折り紙が大好きなので、この二つを組み合わせた仕事をしていきたいと思い、1993年にイスラエル折り紙センターを設立しました。
私は、折り紙が幾何学の学習に非常に有効であることも知っていました。でもあの頃は、まだインターネットなども今ほど普及していなかった時代です。まずは「折り紙とは何か」をイスラエル人に説明するところからセンターの活動を始めました。折り紙を普及させること、そして折り紙好きな人たちが集って心地よい空間で折り紙を楽しめるコミュニティーを作ることを目指したのです。
イスラエルには折り紙も、折り紙の本もありませんでした。今のように海外から気楽に注文できるということもなかったのです。そこで私は、誰でもが親しめる簡単な折り紙の本も作りました。全てがゼロからのスタートだったと思います。

折り紙センターでは、折り紙の作成販売、展示会や折り紙カンファレンス、そしてイスラエル・パレスチナの交流などを軸に活動を続けています。
折り紙には偉大な力があります。折り紙を折っている時は本当の自分、素の自分でいられる。自分がどの民族やどの性別、どの国を代表しているかしていないかは関係なくなるのです。折り紙を折っている時、人はただの人として折り紙を折るのです。
―――イスラエル・パレスチナの交流ではどのような活動がありますか?
ミリ:折り紙センターの付属団体として、2002年に”Folding Together”というNPOを設立しました。政治的な状況などから、残念なことに現在の活動はそれほど活発ではありません。パレスチナ自治区とイスラエルの往来がもっと自由だったころは、パレスチナ自治区の生徒とイスラエルの生徒たちが一緒になって折り紙を折ったものです。現在では、往来が可能な東エルサレムの学校と連携をして活動を続けています。

―――折り紙を使った教育プログラムについて教えてください。
ミリ:始まりは、2012年にシンガポールで折り紙を教えたことです。シンガポールへは短期で行ったのですが、もっと長期で、何度も来てほしいと言われたのです。でも、その頃私の子供はまだ小さかったので、小さな息子を家に残して長期で海外出張に行きたいと、どうしても思えなかった。
そこで、オンラインで折り紙を教える仕組みを作ることにしたのです。そうすれば離れていても折り紙を教えることができます。これが折り紙を使った幾何学教育「オリガメトリア」の始まりでした。
数学博士のドクター・ジョニー・ウーベルマン氏が、オリガメトリアの作成に関わってくれました。対象年齢は幼稚園から中学まで。幅広い年齢層の子供たちに、折り紙を体験しながら幾何学を楽しく学んでもらえるよう、工夫を凝らしました。

2017年にはイスラエルの教育庁にてこのプログラムが正式に認められ、学校教育で利用されるようになりました。
折り紙を使った幾何学の学習は非常に有用なのですが、イスラエルでは学校の先生たちも折り紙について知らない人の方が多かったのです。だからオンラインでの学習は先生たちからも好評を得ました。
折り紙が幾何学の習得率に与える影響に関する実験があります。幾何学の習得率が低かったチームが折り紙を折るようになると、幾何学の習得率が飛躍的に上がり、元から習得率が高かったチームとの差が縮まったという結果が出たのです。
折り紙は左右両方の手を同時に動かします。これは右脳、左脳、両方への素晴らしい刺激になるのです。
また、オリガメトリアを作成した頃は考えも及びませんでしたが、2020年のコロナの世界的流行を受け、このプログラムはイスラエルの多くの学校で利用されました。
2020年までで150校、約35,000人の生徒が利用していたオリガメトリアも、今では600校、約140,000人の生徒が利用しています。
―――この教育プログラムの成功を受けて、アメリカの折り紙協会からイノベーション賞を受賞したとうかがいました。
ミリ:光栄なことにオリガメトリアは、世界でも最大級の折り紙アソシエーションである「オリガミU.S.A」からフロレンス・テムコ・イノベーション・アワードを受賞しました。この賞は年に1度、折り紙の世界における最も重大なブレイク・スルー(大きな進歩)に与えられる、栄誉ある賞です。今までの多くの苦労が実った気持ちになりました。

―――最後に、折り紙センターの今後の活動や目標について教えてください。
ミリ:一つ目は、やはり今まで通り、老若男女を問わず多くの人へ折り紙の魅力を伝えていきたいと思っています。最近は、以前折り紙センターで折り紙を学んだ人たちが子供を連れて戻ってきてくれることもあります。私にとってはとてもうれしいことです。
それから、オリガメトリアを進化させた第2世代を作ること。コンピュータを使って、もっとわかりやすく正確に幾何学を学べるように工夫を凝らしたオリガメトリアを現在作成中です。そしてそれをもっと世界中に広めること。これが私の次の目標です。
コロナで受けた影響もあり、折り紙センターの運営は決して楽なことばかりではありません。でも、折り紙は私の人生に必須なことです。
折り紙を折るということは私にとって得ることでもあり、与えることでもあります。例えば、折り紙センターで作成販売している折り紙は、生活や就業に特別な支援やサポートを必要とする社会的弱者の方々による労働によって支えられています。そうやって、お互いが得て、与えているのです。
そして、Folding Together のプロジェクトで共に学んだ子供からは「相手も同じ人だということを知ってから、私の中の恐怖はだんだんと消えていった」という言葉を聞きました。この言葉を聞けただけでもやってきてよかった!と思えるのです。
私が折り紙センターを作ろうとした過程で、また様々なプロジェクトを行おうとした際に、今までどれほどの「No!」を突き付けられてきたかわからないくらい、困難もたくさんありました。それでも私は、どんな時でも自分のやっていることが間違っているとは思いませんでした。時が熟していない、相手が私を理解しきれていない、そう思ってやってきました。
それは、私が折り紙を選んだのではなく、折り紙が私を選んでくれたからなんです。私は自分の仕事がとても大好きで、誇りをもっています。
―――今日はステキなお話をたくさん聞かせていただいて、どうもありがとうございました。

自身も折り紙芸術家であるミリさん。教育と折り紙を組み合わせ、様々な形で活動をしている彼女の姿は自信とやる気がみなぎっていて、とても魅力的です。
日本で生まれ育った私は、子供のころから折り紙は身近にあったにもかかわらず、彼女のプロジェクトや作品の話を聞くまで、折り紙にそんなたくさんの可能性があることに気付きませんでした。
折り紙の魅力と可能性を最大限まで引き出す彼女は、折り紙と相思相愛と言えるような関係で、うらやましくもあります。彼女のおかげで、イスラエルの折り紙センターで、日本の伝統文化のすばらしさを再確認出来たことがうれしいです。
Origametria Website : https://www.origametria.co.il/
Israel Origami Center : https://www.origami.co.il/