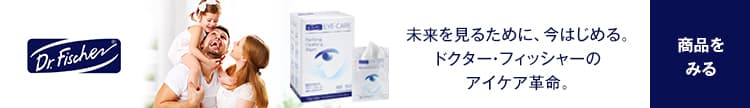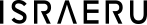アリー・アブ・ミッド・クルディ
アッコ旧市街にそびえる灯台の近くにレストランを構えるアリー・アブ・ミッド・クルディの朝は、大きな片手鍋をコンロにセットすることろから始まります。鍋いっぱいにひよこ豆を入れて水で満たすと、その黄金の豆が、シルクのように滑らかに、バターのように柔らかくなって、お客様に出せるようになるまで、それはそれは優しく煮込んでいくのです。
「フムス(訳注: ひよこ豆で作るペースト状の料理)がベースであることは確かよ。」と、アリーは語ります。「でも、それをどうアレンジするかが私の腕の見せ所。」他の、上品なフムス料理を出すアッコ市街の有名レストランとは異なり、アリーのフムスは、「たとえお客さんが来なくったって」あくまで彼女家伝の調理法にこだわって作られています。その食べ応えは、ややもすると粗く、味を特徴付けるタヒニ胡麻も、他の店のフムスとは異なり、ほんの少しだけ軽く振るに留めます。
「私がアッコにフムスのお店を出すと言ったら、最初は、お前、気でも触れたのか、と言われたものです。だって、街はフムス料理店で溢れかえっているし、それこそ神話的な地位にまで上り詰めたお店もいっぱいありますからね。でもね、私は、私が何をすべきかをちゃんと分かっていたし、どうすればいいのかも分かってました。神様はね、自分の夢を信じてる人を助けて下さるもんなんです。いや、そりゃあもう大変でしたよ。でもね、その大変さも含めて本当に楽しかったし、満足もしてますね。」
アリーは、5人姉妹の末っ子として生まれ、古都アッコの狭く細い路地で育ちました。母親の経営する土産店と、隣り合った灯台の名前に由来する父親のレストラン「ミグダル・オル」との間で、その少女時代を過ごします。その父親の店は、1950年代に、様々な種類のサラダとともに煮込み肉のシチューを出す店としてオープンしました。学校が終わると、もうほぼ第二の家のようになっていたその父親のお店に直行するのが、彼女の子供時代の習慣でした。
学校を卒業すると、家庭崩壊してしまった家族や悩める若者たちを助けたいという情熱に駆られ、犯罪学や社会学を学び始めるとと共に、父親のレストランとの関わりも残しておきたい一心から、最新の設備に関する勉強も同時に始めます。2000年には、健康状態の悪化から、父親のレストランはその50年の華々しい歴史に幕を下さざるを得なくなり、その後は辛うじて母親の土産店の収入だけで生活を維持するような状態になってしまいました。
アリーといえば、12年間に渡る福祉活動を通じ、街の中の打ちひしがれた若者たちの現状を目の当たりにする毎日を送ってきた結果、自分が燃え尽きてしまっている事に気が付いてしまった時期でした。変わらなければ、と必死になった時期でもあります。そして2015年、父親の死から数ヶ月を経て、父親の店と同様、灯台の近くに、彼女自身のフムス料理店を開くに至るのです。店の名前は、父親の思い出にちなみ、「エル・アベッド・アブ・ミッド」と名付けました。
彼女が厨房に再び立つ決心が出来たのは、一つには、創造力に満ち、希望と楽しさにあふれ、快適さをも追究したそのキッチンスペースに由来することは確かでしょう。彼女は、アラブの街にある平均的な家々の台所で長い間作られてきたにも関わらず、レストランではほぼ出されることのなかった、そしてこの地方以外では全く知られていなかった、そんな伝統的なアッコの家庭料理を出す決心をします。例えば「トリディ」という料理は、焼いたピタパン、煮込んだひよこ豆、炙ったアーモンド、そしてサムネーと呼ばれる発酵した澄ましバターを使って作られ、父方の家系で300年間もの間受け継がれてきた料理です。
アリーの店は、完全に彼女のワンマンショーで成り立っています。毎朝、漁師から魚を買い付けるために港に出向き、市場で野菜を仕入れ、全てに渡って自分自身で必要な食材を揃えます。香辛料とそのブレンドは、彼女の夫が経営するスパイスショップから仕入れます。オリーブオイルは、彼女の友人がラメの町の近くで作った物が使われています。午後4時、料理を作り、お客様にサーブし終わった後、店を掃除してエプロンを外すと、彼女の1日は終わります。「食べ物は人生。でもね、毎日を忙しく働いている者にとって、人生はちょっと短すぎるわね。」
「フムスの道の上で」に関して
「フムスの道の上で」は、三人の才能ある筆者によって書かれた、意欲的な著作です。彼らは、魔術師(HaKosem 訳注: ヘブライ語で魔術師)とも呼ばれるアリエル・ローゼンタールの店をまず訪ねます。但し、彼の司るマジックは、シルクハットからウサギを取り出す類のものではありません。どちらかといえば、魔法使いが錬金術を通じて、あらゆる元素から何かを作り出す行為に近いものがあります。美味しそうに黄金色に焼けたナスや、赤身と脂身を絶妙なバランスであぶり焼きにしたシャワルマ(訳注: ピタパンでサンドされた、中東ローカルのケバブサンド)が代表的な料理ですが、やはり極め付けはひよこ豆料理で、そのクリーミーなハマスやサクサクしたファラフェル団子(訳注: フムス同様、ひよこ豆で作る中東版コロッケ)を求めて、世界中から人々が集まってくるのです。
この店は、ローゼンタールのひよこ豆に対する夢と情熱から生まれ、フムスの物語を世界に対して紹介する店となりました。その日、料理ライターを前に、シェフのオルリー・ペリ・ブロンシュタインとクリエイティブディレクターのダン・アレキサンダーを呼んで話が始まると、その会話が豆讃歌となるまでにたいした時間はかかりませんでした。
レバート地方(訳注: 地中海の東側沿岸地区。キプロス、エジプト、イスラエル、レバノン、シリア、トルコなどを含む一帯)において、フムス料理は男性の専門特許と考えられており、女性の経営するフムスレストランは非常に稀な存在でした。昔から、そして現代においても、栄養たっぷりのフムスは朝食の定番メニューで、ハードな一日を送る人々のエネルギー源になっています。そして、昔から続く由緒ある港町であるイスラエル北部の街アッコで、二人の女性が、フムス料理店にぶる下がったこの昔からの慣習を壊して、それぞれの活動を始めたのです。
この本では、世間でひっきりなしに議論されている、この黄金の豆の起源はどこにあるのかというテーマを、人々でごった返すカイロの雑踏から、ガザの狭く細い裏通りを経て、ジャファ、テルアビブ、エルサレム、ナザレ、アッコ、ベイルート、そしてダマスカスにまで追っていきます。様々なレシピ、物語、記憶、エッセイ、讃歌、絵画、そして街の写真が、様々な国籍と信仰を持った、様々な料理人、料理ライター、写真家、研究者、哲学者、歴史家、そして科学者たちの膨大なリストと共にその中で語られ、掲載され、ハマスがそれぞれの地で、その地の食文化、歴史、伝統、政治、懐古、果てはナショナリズムにまで、どのように大きな影響を与えたのかを紹介していくのです。
簡単な作業ではなかった、などという通り一遍の表現では言い尽くせないほどの取材と構成内容をこの労作は持っています。そして、一般の家庭内ではある意味「地雷を踏むような食材」として悪評の高いひよこ豆が、家庭の食卓を超えて、政治領域の議論や、他国の文化の盗用、そして文化の起源に遡るとろにまで踏み込んで、いかに強烈な化学反応を引き起こしてきた特異な食材であったのかを詳細に解き明かしていきます。しかし、その最後は、古代の豆が、様々な、国籍、年齢、宗教、政治信条などの困難を乗り越えて、その地域に住む人々の心をどう魅了し、想像を掻き立て、胃袋を鳴らしてきたかという、ラブストーリーで締め括られるのです。


ソウヘイラ
1957年生まれのソウヘイラの夢は、教師になることでした。彼女の父親が60年代に開いた「アブ・ソヒル・フムス」は、80年代初頭の父親の死後、母親と二人の兄弟に引き継がれます。しかし、兄弟の死、そして母親のキッチン内での怪我で、1993年、結局ソウヘイラがこの店のキッチンを預かる事になりました。
「自分の人生計画ではこんなことは考えてもいなかったわ。」と彼女は強調します。「でも、この店は家族を養ってきたお店だし、この店が将来もちゃんとやっけるように、誰かが面倒を見なければならなかったのよ。」そう、彼女は自身でフムス料理店を経営することなど考えてもいなかっただけでなく、その店が、その世界を代表するような店になるとは思ってもいませんでした。
若い頃、「アブ・ブラヒム・フムス」で修行を積んだ父親は、どうやったら美味しいフムスが作れるのかをそこで学びました。そのレシピは今でもその時のまま、全く変わりありません。毎朝5時、ソウヘイラは25キロのひよこ豆の調理を始めます。水以外何も加えず、ベルベットのように柔らかく、そしてクリーミーになるまで、ひたすらひよこ豆を煮込むのです。お客様が、ボウル一杯の新鮮でホイップされたての暖かいフムスをいつでも食べられるよう、ソウヘイラは、彼女の姉妹や姪たちと共に、日がな一日、小さなバットにフムスを作り続けます。この食堂で使われる材料は、全てハイファの近郊で採れたものに限られています。タヒニ胡麻には、ナザレにある、ソウヘイラ同様女性経営のアル・アルズ・タヒニという食材会社の、品質の高い、香り豊かなものが使われています。
朝の8時、その日最初のお客様が食堂のドアを開けて入る頃、いや、それよりもちょっと前から、食堂の前には行列ができています。フムスに加え、タヒニ、シャクシューカ(訳注: トマトソースと卵のグリル)、クッバ(訳注: コロッケの一種)、ファラフェル団子など、どれも評判が高い料理がメニューに並び、サラダと共に供されます。ソウヘイラは、いつもの場所で、お腹を空かしたアラブ人やユダヤ人、地元の人達、旅行者、男性、女性、子供など、様々なお客様の前に立ち、一人一人の目を見ながら、料理をよそっていきます。どのメニューもどんどんとはけていき、そうやって午後5時、全ての料理が売り切れると、ソウヘイラの一日が終わります。
ソウヘイラに、他の店のフムスと比べてどう思う?と聞くと、「私、他のお店のフムスを食べたことがないのよ」という答えが返ってきました。しかし彼女は、伝統的なアラブ料理、例えばマクルバ(訳注: 挽肉・野菜・お米を混ぜた料理)や野菜の詰め物、ファティール(訳注: 一種の、揚げたおかずパン)、そしてもちろんフムスの料理を楽しんでいます。
2003年度のアッコのハマス王(女王、ではないですよ!)に輝いた実績は、美味しいフムスを通じて人々を幸せにしたいという、何十年にも渡って持ち続けきた彼女の父親の情熱と想いが生きた結果だと感じています。
少なくともこれがフムスの持つ力であり、世界をより良いものに変えていく役割を、その一部として彼女も担っているのです。
Words by Nomi Abeliovich Photos by Yaron Brener and Eilon Paz