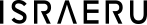イスラエルの世界遺産をご紹介するシリーズ第3弾。
今回は、2005年に世界文化遺産に登録された「聖書時代の遺丘群」です。
旧約聖書にも登場する3つの丘の魅力を掘り下げていきましょう。
なぜ3つの丘がセットで世界遺産?
イスラエルの中で、4つ目に認定された世界遺産が「聖書ゆかりの遺丘群」。
同国各地に200ほど残っている遺丘の中でも、特に代表的なメギド、ハツォル、ベエル・シェバという旧約聖書にも登場する3つの丘(テル)が対象となっています。
この3つの丘が世界遺産に登録された理由は、旧約聖書に登場しているからということだけではありません。
3つの遺丘は、青銅器時代から鉄器時代の都市の富と権力が示されていて、紀元前6世紀まで数千年間存続していたようです。
また、長年にわたって磨かれてきた水利システムによって発展したことも遺跡から見て取れます。
そして、宮殿や要塞などの都市計画の跡が見られるとともに、聖書の時代の歴史的意義が加わっているのも特徴的です。
旧約聖書に11箇所も登場する場所「メギト」
交通の要衝にあり、軍事的な戦略拠点として戦火が絶えることのなかった「メギド」。
古代から多くの戦いが繰り返され、破壊された街の上に新しい街が建設され丘(テル)のようになっているため「テル・メギド」と呼ばれています。
メギドは、カナン人の時代からエジプト、イスラエル、アッシリア、ペルシャと支配されたため、25層もの都市遺跡が重なっています。
また、旧約聖書には「メギドの丘」の記述が11箇所あり、戦いの場として描かれています。
さらに、新約聖書の「ヨハネの黙示録」に記されている「世界最終戦争の起きる場所ハルマゲドン」は、メギドの丘を指すといわれています。
なお、メギドの発掘調査は何度も行われていて、鉄器時代の地下灌漑施設(ちかかんがいしせつ)やソロモン王の厩舎(きゅうしゃ)と考えられている建物、世界最古のキリスト教聖堂の跡などが発見されています。

遺丘群最大の丘「ハツォル」
イスラエルの遺丘群の中でも、最大の広さを誇る「ハツォル」。
紀元前2000年紀には既に2万人が住んでいたと言われており、この地域で最大の都市だったといわれています。
しかも、この丘の層の数は21。エジプトとメソポタミアを結ぶ道筋にあり、肥沃な土地と豊かな水があったため古代から発展しました。
また、城壁の中には豊かな地下水があったため、それを汲みだすため深さ40mまで行ける階段が作られています。
なお、ハツォルは旧約聖書の『ヨシュア記』『士師記』『列王記上』『列王記下』で触れられている場所。
現在でも、後期青銅器時代に建造された大規模な宮殿の跡が残っています。
豊な街でしたが、紀元前732年、アッシリアに占領され破壊されたと言われています。
ちなみに、ハツォルは1955年から発掘調査が続けられていて、2013年には古代エジプトのスフィンクス像の一部が発見されました。これは、エジプト王からハツォル王に贈られた贈答品であると考えられています。

水に恵まれた計画都市「ベエル・シェバ」
メゲブ砂漠の北に位置する古代イスラエルの最南端の街として栄えた「ベエル・シェバ」。
紀元前12世紀頃からイスラエル人が集落を作って住み始めた街は、戦いのため崩壊と再建を繰り返し15層の遺丘(テル)になっています。
ベエル・シェバとは「7つの井戸」という意味で、旧約聖書の『創世記』にてアブラハムが井戸に関する誓いを行ったとされる場所。街には灌漑(かんがい)施設も造られていて、雨水は地下の貯水池に溜められるようになっていました。これは、敵に攻められても、水が飲めるように造られたものだと考えられています。
また、すべての道が広場に通じるように建設された「計画都市」で、要塞として発展しましたが、紀元前701年にアッシリアによって破壊。このことは、歴史的に重要な出来事として旧約聖書にも登場します。
なお、ベエル・シェバは1990年以降、大規模な復元作業が続けられています。

聖書ゆかりの遺丘群は、青銅器時代と鉄器時代の文明を垣間見れる貴重な世界遺産。
かつて、住民たちが中東全体で交易をしてていたこと、水利システムを含めて建築物が発展していたこと、そして他の都市にも大きな影響を与えたことが世界遺産認定の大きなポイントと言われています。
また、聖書にも記載のある場所であるということもポイントのひとつのようです。
イスラエルには、日本ではあまり知られていない世界遺産がまだまだあります。
次回も、詳しくご紹介しますので、お楽しみに。