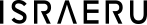イスラエル出身の“映画界の鬼才”アモス・ギタイの新作が、11月5日まで開催されていた東京国際映画祭のコンペティション部門にエントリー。伝説的な映像作家の新作に、大きな注目が集まりました。
“映画祭の華”コンペティション部門に選ばれた問題作
10月27日から11月5日まで、世界110の国と地域から映画人が参加し、184作品が上映されたアジア最大の映画祭「第38回 東京国際映画祭」。コンペティション部門には、たくさんの応募の中から15作品が選ばれ、審査委員やメディア、一般の観客が上映に詰めかけました。その中でも異彩を放っていたのは、イスラエルのハイファ出身で、世界の美術館で特集上映が組まれている映像作家アモス・ギタイの新作「ポンペイのゴーレム」。詩的な映像の中に込められた哲学的な思索や社会へのメッセージに、多くの人が感銘を受けました。
【あらすじ】
『ポンペイのゴーレム』は、2025年6月にイタリアのポンペイで開催された演劇祭で披露された、アモス・ギタイ演出による舞台劇『ゴーレム』を記録したドキュメンタリー。中世ヨーロッパを舞台に、カバラ神話に登場する土人形ゴーレムにまつわる物語が展開します。
舞台劇のドキュメントとフィクションとを大胆に交錯させ、古代の神話と現代の政治的現実を架橋する野心的な試み。西暦79年のヴェスヴィオ噴火で地中に埋もれた古代都市、世界遺産に登録されているポンペイに残された劇場の廃墟で上演された舞台劇『ゴーレム』とともに、歴史と現在とが交錯する詩的なヴィジョンが立ち上がります。

歴史と記憶が刻み込まれた地で上演された舞台芸術
「ポンペイはまだ廃墟なんです。ポンペイという場所は、自然災害によって一瞬にしてすべてが埋もれ、時間が止まったように保存された場所でもあります。つまり、『破壊されながら保存されている』という矛盾を抱えた場所なのです。今回は、あえて歴史と記憶が極めて濃厚に刻まれた場所―ポンペイで上演しました」と語ったギタイ監督。
映画のクライマックスでは、ポグロムと呼ばれるユダヤ人に対する集団的迫害行為について切々と語られ、実際にビジュアルで描くことなく役者の台詞で語られただけにも関わらず、おぞましい描写に暗澹たる気分にさせられました。その痛ましい描写は、たとえ目を背けたい現実であっても、そこから目をそらしてはいけないという、ギタイ監督のメッセージとして受け止めました。

他者に思いを馳せ、理解しようとすることの大切さ
多種多様な人種や民族、9つの言語が登場する本作ですが、とくに印象に残ったのがイディッシュ語。ギタイ監督は、「イディッシュ語というのは、ディアスポラの言語なんです。つまり、固有の土地を持たない言語であり、しかもそれは迫害を受けた人たちの言語です。主にキリスト教徒からヨーロッパのユダヤ人たちが迫害を受けていた時代に、何世紀にもわたってその迫害に耐え抜く中で使われていた言葉がイディッシュ語でした。本作品で、私はその言葉を復活させたいと思ったのです」と語っています。
映画のフィナーレでは、ゴーレムに救われた物語を離れ、さまざまなルーツと生い立ちを持つ演者たちが自らについて語ります。インタビューで「自分とは異なる立場の人の感情や思いを考え、理解しようとする―そうした橋を築くことこそが、今の社会の中で、そしてこれからますます重要になっていくことだと思います」と語ったギタイ監督。圧倒的に美しいビジュアルのドキュメンタリー作品を通じて、すべての民族に『分断の時代を、私たちはどう生きるべきなのか』を問いかける作品です。

映画祭で注目を集めたアモス・ギタイ『ポンペイのゴーレム』が、今後、劇場公開や特集上映で鑑賞する機会があることを願っています。
Golem in Pompei ポンペイのゴーレム
2025年、フランス
フランス語、イディッシュ語、アラビア語、ヘブライ語、スペイン語、英語、ロシア語、ドイツ語、英語
Amos Gitai アモス・ギタイ

1950年、イスラエル・ハイファ生まれ。パリのポンピドゥー・センター、ニューヨーク近代美術館MoMA、ニューヨークのリンカーン・センター、ロンドンのBFIなどで大規模なレトロスペクティブ上映が開催された。長短編のフィクション、ドキュメンタリー、実験作品、インスタレーション、演劇作品など多様な形式を含む90作品以上を制作している。
*アモス・ギタイ監督のコメントは、東京国際映画祭のイベントレポート(取材、文:小城大知/通訳:藤原敏史)から引用しています。