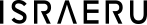今回紹介するダビデ・アディカ氏と出逢ったのは、とある美しい秋の日のこと。イスラエルで名の知れたフォトグラファーである彼が住まいとスタジオを構える、地中海沿いにあるヤッフォ港でのことでした。一番のお気に入りであるという、友人のフィリップ・パゴウスキ氏が描いたハートと目があしらわれたコムデギャルソンのTシャツを着て現れたダビデ氏は「素晴らしいフォトグラファーには心と目が必要であり、私も作品を撮る上で常に探しているものでもあります。」と語ります。今回彼と話をする中で、日本文化、特にファッションとの強い繋がりを感じました。

写真との化学反応
エルサレムで育ったダビデ氏は、いつもアートと美学に惹かれていたと語ります。
「常に視覚的記憶があり、アートは自分にとって愛してやまないものであることは明確でしたね。ただ、それが趣味以上のものであるかどうかは不明確だったため、大学一年生の頃は化学を勉強していました。しかしこれは自分がやりたいことではないと感じ、エルサレムにあるベツァレル美術デザイン学院で写真を学ぶことにしたのです。」
写真は美学と技術の組み合わせであり、この芸術的な融合は、彼の志とよく合うものでした。そして卒業後、彼は講師としてベツァレル美術デザイン学院で写真を教えはじめ、20年後には写真学部の学部長を務めることになりました。
接点としての写真
「私にとって写真とは、好きなものたちとの接点なのです。ここで言う好きなものとはアートやデザイン、ファッションや建築だけでなく、社会学、環境そして行動主義などです。写真はまるでタコのようですね。多くの文化的側面に手足を伸ばし、一つの場所でまとまります。」
卒業後、彼は商業用写真とアーティストとしての作品用写真をそれぞれ撮影していましたが、彼にとってその二つの間に大きな差はなく、あくまでも同じフィールドのものとして捉えていました。料理本に使う料理の写真でも、展覧会に使うポートレート写真でも、常に熱いパッションを持って臨んでいます。

「私は修士号を取得する時に”人を撮る時はオブジェクト(物体)のように、オブジェクトを撮る時は人のように”と言われた事があります。当時はそれがどのような意味合いを持つ言葉か判りませんでしたが、いつも心に留めていました。オブジェクトは人々や社会、文化に対してどんな物語を語っているのか、また人々はオブジェクトや素材とどのような関係性を持っているのか、常に試行錯誤しています。」
彼はとあるプロジェクトで、自分自身の起源であるミズラヒ(アラブ系ユダヤ人)を題材としました。これはイスラエル建国から今日まで続いている複雑な社会的および政治的な問題ですが、彼は作品の中でこの難しい問題について、これまでほとんど触れられていない点についてもあえて触れることにしたのです。
彼にとって一番身近な環境である家庭の中にあるオブジェや食べ物を被写体とした写真シリーズを展開し、その色合いや構成、素材から場所や起源に関する問題を提起しました。
「私にとって地域社会の問題に取り組むことは極めて重要です。私が作り出す作品の内容や題材は、私が来た場所と繋がっています。視覚言語や美学に国境はないのです。」
エルサレム美術館で開催された、イスラエルアートにおけるミズラヒの作品をテーマとした大きな展覧会で発表された彼の独特かつ新鮮なアプローチは、キュレーターたちの目に留まり、その後グループ展での出展するよう誘われました。そしてここから、彼のアーティストとしてのキャリアが始まり、国内外で行われる数々のプロジェクトや本、雑誌、展覧会を手掛けることとなります。
空間
彼の作品のビジュアルランゲージ(視覚言語)は、写真といった枠に収まるものではありません。デザインと建築への興味は、写真がギャラリースペースと出逢う展覧会で力を発揮します。
「私の作品におけるストーリーは、写真と空間の関係に深く結びついています。そしてそれらは正確な瞬間に一体化します。ギャラリー内の全ての要素がストーリーを語らなくてはなりません。私の好きなものが全て一緒に存在し、一つのものを創り上げるパーソナルな言語を発見しました。」

ギャラリーのスペースは三次元構造、色塗られた壁、そしてオブジェクトによってしばしば変化をもたらします。繰り返しとなりますが、写真とはイメージ、オブジェ、空間、時間といった要素を点と点で結ぶ要素なのです。

ダビデ氏の作品は、スタジオ撮影においても屋外撮影においても、常に段階的に行われ、各ショットにたっぷりと時間をかけて丁寧に撮影を行います。
「私はどこでにでもいるようなフォトグラファーではないですね。屋外撮影の際も、私が求めているものを意識し、それを見つけるのです。冒険ですよね。どんなに事前にイメージしていても、写真を撮るときには魔法のような瞬間があり、現実が予期せぬ偶然とアイデアを一つの永遠の一瞬として閉じ込めます。」

日本とヤッフォの出会い
「私は日本と、精神においても感情においても、とても深く繋がっています。前世が関連しているのではないかと思うくらいです。日本の美意識、秩序、自制といったことにいつも惹かれていましたね。一度、日本語には背景のような言葉がないと聞きました。日本人にとって、表にあるものも裏にあるものも全て重要だからです。」

「私はこのコンセプトに同感しています。実際、私の作品において、背景は被写体と同じくらい重要なのです。」
ダビデ氏が日本文化と初めて出逢ったのは、写真家の荒木経惟さんと杉本博司さん、デザイナー川久保玲さんといった著名な人々の作品でした。
「最初にイメージに強く魅了され、深く感動しましたね。日本を訪れたことで、日本文化を理解し、作品の背景に込められた意味を理解しました。日本のファッションやアートに対する全く新しい理解を与える文化的、歴史的そして伝統的コンテクストとして位置づけできるでしょう。私にとって川久保さんの作品は前衛的でしたが、伝統的な柄とシンボルに基づいていることを知り、それはもっと深い意味を持っていることに気付いたのです。」

日本旅行で触発されたダビデ氏は、2016年にアーティストのヒラ・トニ・ナヴォクと一緒に”ゴールデン・ハンズ”という展覧会を開催。二人は数か月間、東京で生け花を学んだ後、工芸と美を神聖化する異文化を扱うという展覧会のコンセプトに大いに貢献することとなるたくさんのアイディアと一緒に、イスラエルへ戻りました。彼らの展覧会のロゴは、東急ハンズのロゴが参考となっています。

肖像画への時間
現在、ダビデ氏は講師としての活動と新しい展覧会の準備で忙しい日々を送っています。
「今生きている時代のせいなのかどうかはわかりませんが、長い間主にオブジェの撮影を行ってきたので、また人々の撮影に戻りたいと思っています。ポートレート写真を通じて、一つのフレームで物語を語りたいのです。私が知っている人も知らない人も、ジェンダーや文化を越えて撮影したいのです。」
ギャラリーで彼の新作を見るまでの間、ぜひダビデ氏のインスタグラムで彼の作品を楽しんでみてください。「Running Diary」というシリーズがあるのですが、これは彼が日課であるビーチ沿いでジョギングをする際に撮影したもので、海を見つめて座る人の後姿を写したものです。彼の目と心は、私たちが日常の中で見落としがちな詩的な瞬間を止まることなく探し続けています。
公式ウェブサイト