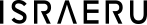日本とイスラエル、両国のビジネス連携はここ10年ほどで飛躍的に拡大しているのは、皆さんもすでにご周知のとおり。今日は、両国に関係のあるビジネスを職業としている女性たちでつくられたネットワーク、「IJ-WIN」(現在は「NEW-IJ」として活動)を取材しました。

目次
どんな既存の枠にも縛られない。強みは柔軟性と自由な発想。
IJ-WIN(現NEW-IJ)は、日本ーイスラエルのビジネスイベントで顔を合わせた日本人とイスラエル人の女性を中心に結成されたネットワーク・グループ。実は、筆者である私もそのメンバーの一人なのです。
グループメンバーはそれぞれ本職が別にあり、IJ-WIN(現NEW-IJ)の活動は無償で行われています。法的な根拠がある「団体」ではありませんが、日本からのビジネスグループにイスラエルの企業を紹介するイベントや、家族の問題で困難に見舞われている女性のためのチャリティーイベントなどの実績があります。

グループの目標は「日本・イスラエルの関係強化」および「女性の社会進出」。これらの目標に関連づいた活動ならば、ネットワークで協力者を得て、自由に活動できるのです。
こう聞くと、とらえどころがなく何をしているのかちょっとわかりにくいところもあるようですが、「そういうところが、逆に私たちの強みとも言えるのです」と、メンバーの一人、ミリ・ゴランさん。
「既存の枠にはまらないからこそ、文化的な活動もビジネスも、そしてチャリティーも、私たちは自由に実施することができます。柔軟性と自由な発想という点には、自信があります。何しろ、私たちは皆、片手に乳飲み子を抱えたままたまった洗濯物と洗いものを横目に、向こう3日先の献立を考えながら仕事を続けてきましたから。外から決められたやり方に固執したり、権威を根拠にする枠組みがなければ先に進めないなんて考えは、とっくの昔に手放しています」と、力強く笑います。
イスラエル・日本、両国の社会にインパクトを与えたい。そのために、協力は不可欠。
イスラエル在住40年を超える、ヨスティング中村知子さんは言います。
「私は、イスラエルと日本の橋渡しとなるビジネスを30年以上前から続けています。いつも思うのは、このふたつの国は、磁石のS極とN 極のように、真逆の性質を持っているということ。それだけに、この両国が協力し合えれば素晴らしい相乗効果が生まれると思うんです。私は両国の橋渡しをして、社会にインパクトを与えたいと思っています。IJ-WIN(現NEW-IJ)のメンバーで協力し合える環境はとても重要です」
そして、日本の働く女性については「イスラエルでは女性も、結婚しても子供がいても働くのは当たり前です。そして日本でも、今は働く女性というのは珍しくなくなってきているでしょう。そうなれば環境も自然と変わっていくものです。日本社会も、きっともっと変わっていくはずです。イスラエルの女性の働き方や家族の在り方、日本でも参考にできることはたくさんあると思いますよ」と言います。
「女性のネットワーク」とは
実は、イスラエルで日本とのビジネスに関わる私たち日本女性は、イスラエルを訪問するビジネスマンのほとんどが男性で、女性がめったに来ないことに違和感と、ある種の焦燥感を抱いていました。
「日本企業からの訪問者はほとんどが男性だね。女性は来ても、通訳か身の回りの世話役。」日本とビジネスをするイスラエル人にも言われたものです。
通訳や世話係が悪いというわけではありません。それでもビジネスの本質的な意思決定の場面で女性が登用されることはほとんどない。イスラエルから、そんな日本の現状が透けて見えるようでした。
だから、数少ない女性のキーパーソンがイスラエル訪問に来れば、同じ女性として応援したくなりました。頑張ってほしい。日本・イスラエルビジネスの懸け橋になってほしい!心からそう思ったものです。これが、このグループの基本にある思いなのです。

「私はイスラエルで生まれ、日本で幼少時代を過ごし、14歳でイスラエルに戻った、日本とイスラエルのハーフですが、正直なところ当時の日本で、私は女性として将来の多様なキャリアを思い描くことができませんでした。30年ほど前の話です。」こう話すのはイスラエルの法律事務所、ワイス・ポラットで弁護士として働くプリオン詩雷(しいら)さん。
「でも、やはり時代は進化しているし、イスラエルにだって女性にとっての”ガラスの天井”がないというわけではありません。私も、IJ-WIN(現NEW-IJ)を通じて多様性のある社会づくりに少しでも貢献できれば、と思っています。」
イスラエル人女性について
アメリカ、フランス、イスラエルで生活し、ビジネスの経験を持つ小林由維子さんは、イスラエルの女性を取り巻く環境を立場をこの様に説明してくれました。

「イスラエルでは、ほとんどの女性が職業をもって働いており、そして私が移住した他のどの国と比較しても、家族を中心に考える国だと思います。”家族”の形も様々で、結婚を選ばなかった女性でも精子バンクを利用してシングルマザーになる人も多く、また同性カップルや妊娠が成功しなかったカップルも様々な制度や方法で自分たちのDNAを基に子供を持ち、育てることを実現しています。」
そしてそれが可能な背景として、「イスラエルの不妊治療は世界最先端ともいわれています。法の面でも経済的な面でも、国も社会も、女性の不妊治療をものすごくサポートするのです。さらに、”仕事か子供かどちらか一方”という二者一択の発想はなく、またイスラエルの社会全体が”完璧”を求めないということも、この両立を可能にしている理由でもあるでしょう。”自分の幸せ”に対する根本的な価値観が、日本とは大きく異なると思います。」と言います。
もちろんイスラエルにも、女性を取り巻く環境の問題はたくさんあります。
それでも、自分自身が何をしたいのかを自分で決め、自分の将来を自分の手で作り上げようとする貪欲さと力強さがイスラエル人にはあります。
筆者は、「女性は献身や気遣いができることが美徳」だと思い込み、「自分自身」が責任をもって何をしたいのか、どうなりたいのかを真剣に考える努力を怠ってきたという事実を、イスラエル人女性たちに見せつけられた気がしました。
IJ‐WINの次なるイベント(終了)
さて、現在IJ-WINのメンバーは、ネットワークで繋がった日本在住のイスラエル人女性2名、ハダス・クシェレビッチさんとシャロン・アルモグさんも中心メンバーとなり、オンラインイベント「From Planter to Plate」の準備に大忙しです。

”フロム・プランター・トゥ・プレート”
日程:2021年3月2日(火)3日(水)4:00pm~8:00pm(日本時間)
イスラエルと日本のビジネスをつなぐネットワークグループ、IJ-WIN(Israer-Japan Women Innovation Netwaok)によるオンラインイベント。
両国にまたがるアグリテック・フードテック分野のステークホルダーたちが、植物性由来食品および都市農業についてのトレンドについて語ります。
お申し込みは、こちらのサイトの「登録」からお入りください。
https://ja.ij-win.org/webinar
このイベントは、プラントベース食品と都市農業を、日本とイスラエルというテーマで扱うものですが、両国大使館やイスラエルイノベーションオーソリティ、元イスラエル国会議員のミキ・ハイモビッチ氏、ビーガンユーチューバーPeaceful cuisineの高嶋綾也氏、アワー・クラウドやソンポ・デジタル・テルアビブといった、多様なセクターのキー・パーソンが参加予定。
全て、IJ-WINコミュニティーのネットワークで人と人とをつなぎ、日本とイスラエルのフードテック、アグリテックのトレンドを加速させるという目標のもと、メンバーが協力し合っています。
自身もビーガンで日本在住6年のシャロンさんは、日本の食材や伝統的な調理法を取り入れたビーガンメニューの開発をしています。

「このイベントを成功させて、日本とイスラエルに持続可能なプラントベース食品の可能性を広く知らしめたい」と語るシャロンさん。
ハダスさんは日本人の旦那さんと2人の子供とともに、京都在住約10年。大阪大学博士課程で製薬に関する研究のかたわら、ビジネスコンサルタント、起業家としても活躍しています。

「このイベントが成功したら、次は日本で、同じテーマでエキスポを開催する予定です。IJ-WINのメンバーはサポートしあい、時には冗談を言い合い、お互いを尊重しあって活動しています。私は出産直後で子供達も小さいのでスケジュール管理は楽ではありませんが、グループのメンバーで(オンライン上で)集まって仕事を進めるのは本当に楽しい。このネットワークをもっともっと広げていきたいです。」とハダスさんはすでに次の目標を見据えているのです。

一人一人の力は小さくとも、お互いを補える多様な仲間がいれば、大きな力となる。
いつも笑い声の絶えないIJ-WINの会議は、これからも続く両国の関係を象徴している様な気がしています。
IJ-WIN(現在はNEW-IJとして活動)