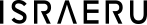イスラエルの世界遺産をご紹介するシリーズ第5弾。
今回ご紹介するのは、2005年に世界文化遺産に登録された「ネゲヴ砂漠の香の道と都市群」。
4つの都市遺跡や城塞、隊商宿、灌漑システムなどが残されている世界遺産を、詳しく掘り下げていきましょう。
ネゲヴ砂漠の香の道と都市群とは?
ネゲブ砂漠は、イスラエル南部に広がる砂漠。ここには、かつてアラビア半島南部で作られる香料(乳香や没薬)を地中海まで運ぶという約2000kmに至る広大なネットワークが存在していました。
その交易路は紀元前3世紀から2世紀まで、砂漠の遊牧民であるナバテア人たちによって利用されたもの。
彼らは各地で高度な技術を活かした灌漑システムを使用し、砂漠で農業を行いながら定住し、交易の拠点となる都市を築きました。そんなナバテア人が築いたハルザ、マムシト、シヴダ、アヴダトという4つの都市遺跡や4つの城塞、2つの隊商宿、交易路の一部が、2025年に世界遺産として登録されました。


特に、4つの都市のうちのひとつであるシヴダでは高度な技術を活かした灌漑(かんがい)システムが発掘。
当時、この地で農業が行われていた証拠となっています。
紀元前1世紀に建造されたナバテア人の都市マムシトは、街の規模はコンパクトですが保存状態がよく、2つのキリスト教の聖堂跡が残っています。西部にあるナイル聖堂は、鳥やフルーツ、幾何学模様などが描かれたモザイク模様の床が有名です。
また、アヴダトは紀元前1世紀に建造。交易路が衰退した後、ワインの生産に力を入れたこの地には、段々畑や水路などがいまも残っています。
特に、ビザンツ帝国時代(330〜1453年)には聖堂と修道院などが建てられており、ワイン生産に使用したブドウ圧縮機がいまでも残っています。

ネゲヴ砂漠の都市群が世界遺産に登録された理由とは?
さて、このネゲヴ砂漠の都市群。なぜ、世界遺産に登録されたのでしょう。
その理由は、大きく分けて2つ考えられます。
そのひとつが、ネゲヴ砂漠の香の道と都市群は、カンラン科の特定の樹木から採取される乳香によって繁栄。
この貿易を通じて、経済や社会や文化、そして周辺地域の交易品や思想までもが、この地に集まったという点。
そして、もうひとつが、本遺跡には5世紀にわたって繁栄した都市や城塞、隊商宿、農業システムなどが残っていて、人類が砂漠の環境に対応してきたということが明確にわかる点。
また、貿易によって物品だけではなく、人々の交流が発生していたという点も評価されています。
こうした極めて稀な状況がしっかりと残されていること、そして独自の文化が生まれたことも、世界遺産登録の決め手になったのだと考えられています。

イスラエルには、日本ではあまり知られていない世界遺産がまだまだあります。
次回もお楽しみに。