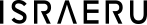とある週半ばの夜、テルアビブ南部の工業地域にあるShai Yehezkelliの工房を訪ねました。通りに全く人影はなく、彼の工房が最上階にあるビルの中も閑散としています。Yehezkelliは、非常に謙虚で愉快な人物ですが、工房の中の彼は、その混沌としたコンクリート製の怪物の中で、小さな天国、とも言えそうな自分自身だけの世界を築き上げているようです。工房の中央で、彼のカラフルで活気溢れた作品に取り囲まれて、このインタビューは始まりました。「僕の基本は、『塗る (= paint) 』事さ。」彼に、作品の描き方を聞くと、こう答えてくれました。「もちろん、時々は『描く (= draw) 』けどね。でも、この二つの行為は、僕の中では、滅多にぶつかり合う事のない、全く異なる表現技法なんだ。」
―――作品の制作過程について、教えて下さい。
Shai Yehezkelli (以下、SY): 僕は、ほぼ毎日この工房に通い、いくつかの作品を並行して進めている。まあ、そんな時でも、やはり集中しているのは1点、多くても2点の絵だけどね。そして同時作業で、パレットペインティングを作っているのさ。それは、紙、木製のパレット、そしてそれ自身で意味を持つまで塗料の残りを塗り重ねた陶器、そういったものからできている。僕の制作過程の特徴は、一つの作品から別の作品へと、それこそ目まぐるしく作業の対象を変えていく事にあるんだけど、それは、それぞれの作品世界の創造と、その作品に将来向き合う事ができるよう、逆にその作品から一時的に離れて疑問を呈する作業、その二つを行っていく事が非常に大切な事だと思っているからなんだ。この制作方法を行うようになって、2年になるかな。いや、もしかすると今日始めたばかりかも。多分、ADHD(注意欠如・多動性障害)なのかもね。
―――では、そんな制作過程では、どんな事にインスパイアされるのでしょうか?
SY:それには、法則もなければ、一貫性もないね。10年くらい前かな、僕は、自身の制作過程を根本から見直し、対象を単なる観察や写真で描くことを完全にやめたんだ。工房で僕を刺激してくれる作業は、対象となるモノを単に写しとる作業ではない、と強く感じたからさ。なんの事前スケッチも、そして考えもなく、タブラ・ラサ、すなわち、全く白紙状態のキャンバスに向かうのが僕の性分なんだ。そうやって向き合うことで、色が語りかけてくる何らかの「そぶり」が、僕を新たな表現へと推し進めてくれ、同時に、僕が絵を描き始めてからずっと持ち続けてきた、幾つかの表現テーマを思い出させてくれるんだ。この表現テーマは僕の頭の中にとても深く刻み込まれているので、いまさらそれを観察し直すなんて事は全く必要ないし、それにその表現テーマ自体、僕の頭の中で新たに加工され、変わってきている。でも、実を言うと、そこが難しいところなんだ。まさにゼロから始めて、一体何が出来上がってくるのか、それを試し、そして発見していく事に大きな意欲をもって臨んでいる訳だけど、そのプロセス自体は、非常な苦痛を伴うものでもあるんだ。色を何度も何度も塗り重ねては消していく、そんなまるで「逆考古学」みたいな作業が僕の多くの作品にはあって、自分が何を追い求めているのか分からない時でも、そんな作業で掘り起こしていくと、必ずそこには新たな何かが見つかるんだ。
―――でも、そうやって無限に掘り続けることも可能ですよね。どうやって作品の完成を見分けるのですか?
SY:いや、そんな、完成を見分ける、なんて事はしないよ。ただ、自分が目指していた地点に向けて絵を仕上げていく過程で、ちゃんと新たなアイデアが生み出せたか、構成、色、そしてその内容といった概念を検証してみるのさ。その時、最も重要な事は、僕が思うに、どんな物語を僕は選び出すことが出来ただろうか、という事なんだ。僕の表現テーマは、常に僕の興味をかき立ててきたもので、それは、僕が育った地のアイデンティティであり、歴史であり、文化である訳だけれど、そういった僕自身の宗教的なバックグラウンドである古代との繋がりが、21世紀の今日に於いても、その絵の中でまだ生きていると言えるかどうか、という事なんだと思うな。
彼の直近の、「Maarava」と題された個展は、マイアミのMindy Solomon画廊で、今年の4月に行われました。
SY:この個展は、西洋という概念の、現代における究極的な定義に焦点を当て、『彷徨えるユダヤ人』への個人的解釈を加えながら、2012年以降に取り上げたモチーフに関しての回顧を行う展覧会だったんだ。
―――では、全く異なる背景と文化を持つアメリカ人たちが、どのように彼の作品を理解し、共感したのでしょうか。
SY:国境を超えて僕の作品を理解してもらう事は、確かに難しいことではあるね。国外で開かれた個展に来て頂いた、様々な人たちと話をしてみると、自分にとって一般的な概念だと思っていたことが、非常にイスラエルだけに特有の、しかも非常に特殊なユダヤの宗教に根ざしたものだったんだって事を、痛いほど認識させられた。でも、そういう意味では、イスラエルでも、アメリカでも、僕の作品への理解の難しさは一緒じゃないかな。僕の作品は、イスラエルの文化にとても深く根ざしていて、海外では、ちゃんとした説明が必要なんだ。
―――そういった事を、制作中に考えたりしますか?
SY:いや、それはないね。画家としてのキャリアが始まった頃、説明が必要な絵画とは、というテーマで友人と議論をしたこともあったんだ。結論は、『説明なんて、必要ない』だったけどね。実際、僕の作品や、カタログ、作品テーマ、アーティストブックといった様々な情報は、ネットを通じてすぐに手に入れることができるし、僕の作品を研究したいとか、背景にあるアイデアを読み解きたい、といったような希望は、ネットを通じてすぐに叶えることができる。大体、絵画それ自体が、作家の一義的な解釈を一方的に見る側に押し付ける、なんてありえないって事は、世界中の誰もが理解しているよね。僕の作品に関しては、特にそうだと思うな。
彼が自身と自身の作品に関して語るこの謙虚な姿勢には、非常に驚かされました。彼は実際、自身の作品評価が自然な流れに任せることを良しとしており、それはまるで、彼が芸術の世界に足を踏み入れたのは、全く偶然のなせる技、と語っているようにも思えるからです。
SY:僕は、高校時代に学校からドロップアウトしてしまい、級友たちが大学に入学する頃、まだ期末試験を受けてるような始末だったんだ。元々は、歴史と文学を学びたかった。でもその為には、大学資格試験(SAT)を受けなきゃならなかったし、そのためにもう一年を棒に振るのは耐えられなかったんだ。結局、ベツァルエル美術デザイン学院にいた友人が、そこを推薦してくれた。僕は、そこで学べる最も一般的な学科って何だろうというのを探したんだ。ベツァルエルを卒業しても、別に芸術家になんてならなくていいんじゃないかって、純真に思っていたからね。でも、ベツァルエルで芸術を学び、探求していったことで、結局この世界に身を置く事になったのさ。
彼の作品を時系列で見ていくと、2014年ごろに、彼のターニングポイントがあった事に気付きます。
SY:絵画を教えるようになって、確かに何かが変わったね。人に教える、という立場になる前は、僕の作品には、ちょっと冷笑めいた部分があった事は確かなんだ。世の中に対して卑屈な態度を取ることを心底嫌っていたからね。僕自身、宗教的な教育環境で育てられたことから、世の中の芸術家に関しては全く無知だったし、芸術というものを、世の中で卓越した分野だとは認めていなかったんだ。でも、ベツァルエルで近代・現代の芸術に接する事で、綿々と続けらてきた宗教儀式が、如何にして宗教的な後光を手に入れたのか、すなわち、ギャラリーや美術館に広がる静寂、触れる事を禁止された芸術作品、そしてその後ろに広がる宗教的なやり取りや超越的な思想について、まさに気付かされたんだ。頭でも、感覚的にも、こういった事柄にどんどん魅了されていった。でもまだ、自身の宗教性や芸術への理解と、全く宗教性を帯びない、しかしとても美しい作品との間には、大きな溝があったんだ。僕は、「観衆を騙す」ような事はしたくなかったし、自身の作品をちゃんと賛美して欲しかった。でもね、単純に絵画を壁に掛けるだけで、それがどんな絵だろうと、至高の価値を帯びてしまう、っていう事に気付いてしまったんだ。絵画を教えるようになり、どのように芸術が人々に影響を与えるか、目の当たりにするようになると、そんなシニカルな物の見方は消えてなくなったよ。代わりに、どんな手段を取ってでも、自身の作品に罪の意識や審判の影を落とすようなことは絶対に避けるようになったんだ。そうやって、自身の作品を豊かで実り多いものにしようとしてるんだ。どうやって作品に深みと奥行きを与えていくのか、まだまだ苦悩しているよ。

彼自身は、自分自身をしっかり理解している人物ですが、同時に彼は、世の中から孤立した自分自身だけの世界を紡ぎだそうとしているように見えます。彼が、自身の作品の中で繰り返し使用するテーマである、人間の力強い容姿を通じて、その部分を理解しようと努めてみました。
SY:自画像を描く事は多いね。単純に自分を描いた、自分に似ている絵、ではなく、概念的な自画像だけど。自分が女性を描くのは、良くないと思っているんだ。そこに描かれるものは、即ちそこで言葉を発するべきだと思っているからね。だから、他人を描こうとはしない代わりに、自身の「エゴ」とも言えるものに似せた特徴を、絵画の中で孤立化させ、浮かび上がらせようとしているんだ。なので、僕の絵画は決して「男の世界」ではないんだ。それは単に「僕の世界」であるだけ、なんだよ。
彷徨えるユダヤ人は、そんな彼の作品に繰り返し登場するモチーフの一つです。
SY:僕を、彷徨えるユダヤ人というキリスト教の伝説にのまり込ませた、とある書物からこのテーマは始まっている。まず、この主人公を、僕自身の考え方、そして僕自身の世間からの孤立という体験に基づいて、しっかりと絵で捉えたいと思ったんだ。もちろん、世間という中に僕は住んでいる訳だし、愛する人もそこには存在してる。でもね、特に最近、イスラエルという国に対して、とても入り混じった複雑な感情が生まれてきている。つまり、ここは自分の国じゃないんじゃないか、などという感情さ。でも、僕は外国で暮らしたことなど一度もないし、どこの国でも心から寛げるような事は一度もなかった。そう、この二重性は、何処にも安住の地を得られず、ひと所から別の場所へ苦しみに満ちた逃避を行い、自身の故郷、という確かな土地を得ることの叶わなかった、一人のとある人物から来てるものなんだ。これは、今日の世界において、単にユダヤ人だけに特有の感情ではない。世界中の難民たちが抱いている感情だと思うんだ。スウェーデンの人々の一部も、絶対に同じ感情を抱いてると思うな。
―――では、故郷、とは何なのでしょう。
SY:僕自身も、私にとっての故郷という地がどこなのか全く分からないし、どうそれを見つけるのかも分からないな。自分の育った場所が故郷?それとも、自身が安らげる場所?はたまた、自分自身の、感傷的なルーツ探しに関連する場所?
こうして、彼との別れの挨拶を交わし、私は彼の工房を後にしました。自身で発した問いに思い悩みながら。
テキスト:Inbal Sinai