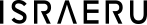2022年は日本・イスラエル外交関係樹立70周年の年であり、近年飛躍的に発展した二国間関係を更に強化することを願った様々な記念事業が両国で行われている。更に、2023年3月には、成田ーテルアビブ間に関係者念願の直行便が就航することになった。
2007年以降、イスラエルとビジネスだけではなく様々な形で接点を持ち続けてきた筆者にとっても、ここ数年の急激な展開は驚きに近いものがある。イスラエルの投資コンサルティング会社の1つであるハレル・ハーツインベストメント・ハウス(HIH)が2022年1月12日に発表した調査結果によれば、2021年の日本の対イスラエル投資額は過去最高の29億4500万ドル(約3400億円、2021年末レート114円換算)になった。
コロナ禍のために少し低迷した2020年は投資額が10億310万ドルであり、ドルベースで約2.9倍となった事がわかる。この額は、同年のイスラエルのハイテク業界への投資全体の12%となり、イスラエルにとっての日本がそれなりに重要なプレーヤーとなってきたことを示している。

2001年からの推移を見ると、2014年、15年あたりから明らかに投資が増加する傾向が見て取れるだろう。振り返ってみると、この頃から両国首脳の外交が活発化している。主なイベントをピックアップすると、
2014年5月 に当時のネタニヤフ首相が来日し、安倍元総理大臣と首脳会談を行う。
2015年1月 に安倍元首相は経済ミッションも連れてイスラエル訪問、政治・経済・安全保障・科学技術など幅広い分野での二国間関係強化に合意。
2015年12月 5月に開始された日・イスラエル投資協定交渉が、4回の交渉会合を経て、協定の本文について実質合意。
2017年5月 当時の世耕経産大臣がイスラエル訪問、共同声明「日イスラエル・イノベーション・パートナーシップ」に署名。
これらの動きに合わせるように日本企業からの投資、日本企業とイスラエル企業との協業が増加していった。私自身には国や産業界の方針についてコメントする力は無いが、この時期も2国間をつなぐ現場にいた一人の肌感覚として、2020東京オリンピックが両国間の関係を密にした切っ掛けの一つであったろうと感じている。
ロンドン五輪を狙っていたサイバー攻撃
2020年の東京オリンピック開催が決定されたのは2013年9月だったが、その前年2012年のロンドンオリンピックでは2週間の開催期間中に2億回以上のサイバー攻撃があったとBT関係者が明らかにしている。
国際的な大イベントがサイバー攻撃対象になることはある種の常識だが、このときに話題になったのは電力インフラがサイバー攻撃対象になった、ということだった。開会式で停電が起こり大きな混乱が発生する、というような脅威に備えて、ロンドンオリンピックのサイバーセキュリティ責任者は様々な危機対応策を施した。

当時の日本でも無論サイバー攻撃の脅威に対する認識はあったものの、それは”情報システム”が攻撃されることによる個人情報や企業の内部情報漏洩のリスクとその対応が中心であり、電力インフラや工場の制御ネットワークなどを制御する”OT(Operational Technology)システム”に対するサイバー攻撃が起こり得るという認識は殆どなかった。
実際、筆者自身が2014年後半からイスラエルのサイバーセキュリティ技術の紹介にいくつかの日本企業を回ったが、「電力や鉄道のシステムは外部ネットワークにはつながっていない」「工場のシステム、ネットワークも独立であり、かつ、独自プロトコルなので外部から侵入されるリスクはない」という声がほとんどであった。
しかし、ロンドンオリンピックを標的としたサイバー攻撃の情報が明らかになるにつれ、政府も産業界も従来のITシステムへの脅威認識だけでは不十分であることを理解してゆく。そこで日本の関係者はイギリスの経験やノウハウを学ぶと同時に、サイバーセキュリティ分野ではアメリカと並んで優れた技術・経験・ノウハウを持つイスラエルの協力を期待した。日本政府が中小企業も含む産業界に対してセキュリティ対策の強化を要請したこともあり、イスラエル側もこれを大きなビジネスチャンスと捉えて積極的にアプローチしてきたのである。
Why Israel
オリンピックを契機とした具体的なサイバーセキュリティのニーズとともに、イスラエルの技術力に関する認知が広まってゆき、その後大きなうねりとなるDX(ディジタルトランスフォーメーション)やオープンイノベーションの流れの中でも、イスラエル企業の持つ様々な独自技術が注目されてきた。そこには、“なぜイスラエルの技術に注目すべきか”“なぜイスラエルに投資すべきか”を説く両国関係機関の地道な努力がある。前述の通り、2017年には両国の政府機関及び関係団体が参加するJIINが設立された。

図の通り、JETROが事務局となり、イスラエルのスタートアップや技術を紹介するセミナーやイベント、メールマガジン、レポートの発行を行っている。技術や投資先企業を探している日本企業や、日本のマーケットに関心のあるイスラエル企業を支援し、両者の連携を促進するための情報提供や紹介を行うプラットフォームとなった。
コロナ禍前はイスラエルからスタートアップが来日してセミナーやイベントに参加したり、日本からのミッション派遣の機会も用意された。JIINのイベントとしては、ディジタルヘルス、投資セミナーなど、既に20回を超えるイベントが開催され、また、駐日イスラエル大使館経済部も毎月のようにオンライン、オフラインのイベントを開催して企業やソリューションの紹介をするとともに、マッチングの支援を行っている。
これらの活動を通して理解の進んだ”Why Israel”とは、
①様々な分野で有望なソリューションを開発するスタートアップが次々に生まれており、ユニコーンとなる企業も多い
②スタートアップを支援し、育成する政府、軍、大学、投資家などが有機的に繋がって機能する”イノベーション・エコシステム”が確立されている
③マイクロソフトやグーグルなど、世界の主要な多国籍企業がイスラエルの技術・人材を活用するための研究開発拠点を置いている
などが挙げられるだろう。実績や競合他社の動向を気にしがちな日本企業としては、③の事実はWhyへの答えとしても大きかったのではないだろうか。
また、同じような観点から日本の大企業はかつてシリコンバレーに注目し、そのマインドセットやエコシステムを学ぶために社員を派遣したり、拠点を置いたりした。しかし、日本人が現地のコミュニティの中に入りこむことは容易ではなく、必要となる投資コストも莫大でなかなか成功事例は生まれなかったと言って良いだろう。シリコンバレーよりは投資コストも安いと期待し、彼らの目が”中東のシリコンバレー”であるイスラエルへ向いた、という事情もWhyの一つとして挙げられるかもしれない。
ちなみに前述のHIHの資料から、日本企業によるイスラエル企業の買収実績も表にまとめてみた。先のグラフの数字の一部となる内容だが、企業名や投資金額から2014年以降の日本企業の活動活発化をより具体的にイメージすることができるだろう。

How Israel
これら2つの図に見られるデータからもわかるように、もはや「なぜイスラエルに投資する意味があるか?」「なぜイスラエルの技術を活用する意味があるか」などを議論する段階は過ぎ、多くの日本企業が自社のCVC部門や外部コンサルなどを活用してイスラエルの企業や技術を探索し、次々に投資を行っている。既に、日本企業がイスラエルへ進出または投資をする際に理解しておくべきイスラエルのビジネス環境や法務・税務について専門的に解説する本、『イスラエルビジネスガイドブック』も商事法務出版社から出版されており、Howの主要なポイントを学ぶことも出来るようになった。

また、駐日イスラエル大使館経済部自体が技術や企業の探索支援サービスを提供しており、日本企業側が関心のある分野や考えている協業のありかたを示せば、適当と思われる候補企業を探し、面談のアレンジメントも無償で行ってくれる。何と言ってもイスラエル人同士のネットワークは太いため、彼らが探せない情報はほとんど無いと言って良いだろう。同様の支援サービスはJETROも行っており、様々な規制や制度、手続きなどだけではなく、具体的なビジネスの相談にも乗ってくれるので、活用しない手はない。

更に有償ではあるが、デロイト・トーマツを始めとする多くのコンサルティング企業が、イスラエル企業・技術の探索活動を支援するサービスも提供している。彼らは法務、税務面の専門知識があるだけではなく、日本人・日本企業とはかなり異なる面の多いイスラエルの企業や人の文化、習慣にも具体的なビジネス経験を通じて習熟しているため、今まであまりイスラエルとの接点がなかった企業にとっては頼りになるだろう。日本とイスラエルとのビジネス文化がどれくらい異なるかを理解するには、『ISRAELI《イスラエル人》のビジネス文化』という本も参考になる。

ただし、投資・協業を上手く始めるためのHowに留まらず、これからは蒔いた種を刈り取る段階にも入る。過去の成功事例・失敗事例の評価から、「歩留まり」を上げるためにはどうすれば良いか、というHowも評価・学習する段階に入っていると言えるのではないだろうか。
先の表に示した企業買収についても、その金額に見合った成果が出ているのかどうか、そろそろ厳しい評価が可能な段階に来ているはずだ。投資には疎く、単なる元技術者に過ぎない筆者にも、この表の中から、買収した企業やその技術を活かせていないと思われる事例は見つかる。
イスラエルを売り込むことに熱心な人々の声に惑わされずに、投資する日本側にとって本当にメリットのあるソリューションであり、ディールであるかどうか、技術的にも経営的にも厳しい目利きが求められるだろう。冷静なPoC(Proof of Concept)やDD(Due Diligence)を経た上での投資判断であれば、思わしくない結果は投資した日本企業側の責任である。なかなかネガティブな情報は開示されてこないかもしれないが、これらの先行事例の分析に基づいた”より良い結果に至るためのHow”も求められる段階に来ている。