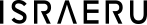2月9日に駐日イスラエル大使館経済部と日本電気株式会社(以下NEC)の共催で ”サイバーセキュリティ大国イスラエル発!最先端技術の活用”というテーマのウェビナーが開催された。前半は、イスラエルに研究開発拠点を持つNECから「今求められるセキュリティートランスフォーメーション」という講演があり、後半は5社のイスラエル企業によるソリューション紹介があった。大変時宣を得た内容であったので、その概要を紹介したい。なお、本ウエビナーはYouTubeで見ることができる。
目次
ダニエル・コルバー経済公使による開会の挨拶
冒頭のダニエル・コルバー経済公使による開会の挨拶では、昨年がイスラエルのサイバー分野にとって記録的な年であることが示された。それは、世界のユニコーンのうち、33%がイスラエル企業であり、サイバー分野への世界の投資のうち約40%はイスラエル企業への投資だった、ということだ。この数字は、如何にイスラエルのサイバー企業が世界から注目されているかを示すものだろう。今年は日本・イスラエルの外交関係樹立70周年を記念する年でもあり、サイバー分野を中心とした両国の経済協力は益々強化するだろうとの見通しを示された。
NECサイバーセキュリティ講演「今求められるセキュリティートランスフォーメーション」
続いて登壇されたのが、NECサイバーセキュリティ戦略本部長 兼 サイバーセキュリティ事業部上席主幹 淵上真一氏だ。淵上氏は、先端技術を必要とする環境の変化からイスラエル技術の活用について說明された。それは、あらゆるビジネスの置かれている環境の変化スピードが早い、という課題認識である。その急速に変化し続けている環境に、どうやって柔軟に対応していくか、こそが“レジリエンス(復元力)”ではないか、と氏は指摘した。
日本電気は世界に7箇所のR&D拠点を持ち、1000名の研究員を抱えるという。日本での開発だけでは急激な変化のスピードに追いつかないところを、イスラエルを含む世界の開発拠点の力を活用していくことで適切なソリューションを提供していく、という方針なのである。
演題の「セキュリティトランスフォーメーション」という言葉はあまり聞き慣れない用語だが、DX(デジタルトランスフォーメーション)とサイバーセキュリティとは一体で考えるべきことである、というメッセージらしい。現在、DXはまさに多くの企業の経営課題であり、クラウドの利用、IoT機器の利用などが進んでいるが、その一方で、クラウドやIoT機器の利用はサイバー攻撃のアタックサーフェース(攻撃を受ける可能性がある箇所)が増えることも意味する。従って、両者をセットで考えていく必要がある、というメッセージと理解した。

イスラエル企業5社によるソリューション紹介
その後、二部としてイスラエルから関連するソリューションを持つ5つの企業の短いピッチがあった。以降、順番に発表の概要を紹介する。
Adaptive Shield

最初に登場したAdaptive Shieldからは、代理店であるマクニカが日本語で說明を行った。
クラウドサービスの利用が増えているなかで、それに比例するようにクラウドの設定不備による情報流出が増えているという。Adaptive Shieldのプラットフォームは、Salesforeなどの様々なクラウドサービスの設定を診断し、リアルタイムでセキュリティリスクを検出するSSPM(SaaS Security Posuture Management)というソリューションだ。
2019年9月に設立された企業ながら、既にグローバルで30社以上の導入実績があるという。
ARMIS

2番手のArmisからは、Armis JapanのRichard Li氏が日本語で說明を行った。
こちらはIoT機器に対応するソリューションである。Li氏によれば、監視カメラ、プリンターなどのIoT機器は、その90%は管理されていないという。ARMISのプラットフォームは、これらのデバイスをエージェントレスで可視化し、脆弱性やリスクを評価するとともに、異常な動作等はリアルタイムで検知・対処する。2015年に創業した企業ながら順調に事業を成長させており、現在は従業員も500名以上、フォーチュン100の企業のうち30社が顧客になっているそうだ。
Mastercard Cyber Quant (旧 Cytegic)

次に登場したのはマスターカードのErika Katayama氏で、2020年にマスターカードが買収したCytegicという企業のCyber Quantという商品を紹介した。この商品は、企業における様々なサイバーセキュリティリスクを自動で評価・診断し、定量化してダッシュボードに示すとともに、定期的にレポートも発行する、というサービスである。マスターカード自身が最大のユーザーであり、その有効性を確認したうえで自信をもって顧客へのサービスも提供しているという。ポイントはリスク分析を定量化する技術とともに、それを技術者だけではなく経営者にもわかりやすく示すダッシュボードである。
PENTERA security

残りの2件は海外からの参加で英語での発表であった。PENTERAの発表者は、テルアビブのAri Kaplan氏で、彼らの会社が今年最初のユニコーンとなったというニュースの紹介から始まった。PENTERAはセキュリティの検証とペネトレーションテストを提供する企業であり、彼らのプラットフォームは自動で24時間顧客のシステムのセキュリティリスクを評価・監視する。攻撃者がどのように考え、行動するか、を理解していることが彼らのペネトレーションテストの強みであり、ユーザは自動検証結果をダッシュボードからいつでも確認することができる。更に、リスク評価の重み付けをし、プライオリティの高いリスクが何であるか、を認識することが出来るようになっている。
Voyager Labs

最後に登場したのはDivya Khangarot氏で、インドからの参加だった。Voyager LabsはAIベースの調査ソリューションで4つのプラットフォームで構成される。オープンWEB、ディープWEB、ダークWEBからのデータを駆使して、ユーザにとっての潜在的なリスクを特定、解析し、実用的なインテリジェンスを提供するクラウドベースのソリューションである。オープンデータのみを扱っておりIntrusiveでないこと、コンテンツ解析をAIが行うことが特徴である。アメリカで、3000社のAI企業のなかから最も優れたインテリジェンスAIソリューションであると評価された。
各企業のピッチに与えられた時間はわずか5分で、概要の紹介レベルの說明ではあったが、各サービスがクラウドの時代に求められる重要なソリューションであることは十分に理解できた。近年、ヘルスケアやFintecなど、幅広い分野でイスラエルのスタートアップの活躍が目立つが、やはりサイバーセキュリティでのイスラエルの強さは特別だろう。この分野のイスラエルスタートアップを継続的にチェックしておくことが必要だ。